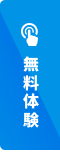人事の歴史を学ぶ!明治時代からの組織と人事の移り変わりについて
皆さん、日本の組織や人事が歴史的にどうだったか、興味はありますか?
このコラムでは、時代の変化に伴って組織と人事実務がどのように移り変わってきたのかを俯瞰していきます。なぜ、こうした時代の変遷を理解することが重要なのかと言いますと、現代の人事実務は、過去の歴史の積み重ねによって築き上げられたものであるからです。
「なぜ、成果主義が取り入れられたのだろう?」「日本は欧米と違って職能主義がメインだけど、なぜそうなったのだろう?」といった疑問に対する答えは全て、歴史の中にあるのです。そして、今後の人事実務を考えていく際にも、こうした歴史の中で築かれた日本独特の風土や文化の側面を考慮しないわけにいきません。歴史的な背景と市場における競争力が企業経営に影響を及ぼします。そして、人事実務は企業経営と密接に連動しているのです。
ここでは、あくまでも人事施策を推進していくために必要な情報を提供するのみに留めます。歴史に関しては諸説ありますし、専門家によっても取る立場が異なることもありますから、そこは通説の歴史に基づいての組織概観であることをご容赦頂ければ幸いです。
また、江戸時代後期から戦後にかけて日本の企業経営や働き方が大きく変化していきますが、時代背景に伴う常識は現在のそれと比べようがありませんので、安易に人権問題やダイバーシティ等へとテーマをすり替えることのないよう、注意を払っていく必要があると思っています。
組織と人事実務の変遷は、明治時代から戦前までと戦後から現在に至るまでの大きく二つに分かれます。まずは、明治時代から戦前に至るまでを概観していきます。
このコンテンツの内容
1.明治時代から戦前に至るまで
江戸から明治へと時代が移り、近代化が急速に進む中で雇用側から見た働かせ方と、労働者側から見た働き方、双方に大きな変化が起こりました。
清を始めとして、アジア全域が欧米列強の支配下に組み込まれていくのを目の当たりにした明治政府は、欧米による占領・侵略から免れ独立を維持していくため、一刻も早い富国強兵の実現に迫られたという時代背景があります。
独立維持のため、富国強兵として殖産工業の推進と軍備の拡充の二つを軸に展開し、その推進力を高めるための教育に力を入れることとなります。この時代の大きな変化に対応する日本人の柔軟さ、忍耐強さ、真面目な気質が経済の拡大に良いサイクルをもたらします。
国や企業が人材を育成する環境整備を行い、スポンジのように多くを吸収する労働者が多くの事業変革を実現していったことで、明治維新からの40~50年程度で西欧諸国と対峙できるほどの国力増強を図ることができたといえます。
この背景としては、江戸時代から続く高い教養や文化があり、日本人ならではの勤勉さや村中で若手を育てていこうとする気概があったことが影響しているといえます。この、人材を育成する仕組みが戦後も形を変えて残り続け、戦後復興を経て日本が世界に名だたる経済規模を誇るまでになった礎となっているといっても過言ではありません。
歴史を知ることは、今後の組織構築と人材育成を考えていくうえで大きなヒントになると思われます。この、急速に進んだ近代化で特筆すべき大きな変化とは、以下の4つです。
②内部請負職人の直接雇用化
③基幹社員と一般工員の格差
④養成工制度による技術者の養成
①奉公人制度から社員制度への転換
江戸時代、主に商売を営む主は奉公人・丁稚制度をとっていました。
奉公人・丁稚制度とは、小さいころから奉公人としてほぼ一年中、主の家に居候しながら商売の基礎教育を受け、やがて後を継いで支店出店や暖簾分けをするといった制度です。
今から考えると、職業選択の自由がないと思われるかもしれませんが、体系的な教育やしつけが行われることのなかった当時、奉公人として修行させることで自らの食い扶持を確保することができたので労働者としてはまんざら悪い話ではありませんでした。また、雇用主も十数年の間、面倒を見ていく中で自らの商売に対するアイデンティティをしっかりと継承することができ、また奉公人の能力や意欲、資質を見ることもできたので、非常に合理的なシステムであったといえます。ある意味、こうした考えは今も変わらないかもしれませんが(苦笑)
大まかな育成の流れとしては、10~13歳程度の男子が丁稚として奉公入りし、当時は十分ではなかった教育やしつけを主が直接行っていました。
昼間は掃除や風呂焚き等の雑務をこなし、夜間は読み書き算盤を習うという形で、商売の基本動作と基礎学習を行っていたのです。15~19歳頃には手代となり、実務を担当しながら商売のイロハを学習していきます。そして、25歳頃には番頭となり、主から暖簾分けや支店を預かる主人として出世していく、という江戸時代ならではの人事制度であるといえます。
この奉公人・丁稚制度は、明治時代以降「仕着別家制」「住み込み給料制」「通勤給料制」「会社員制」と大きく4つの段階を経て今でいう社員制へと移行していきました。
仕着別家制(しきせべっけせい)とは、奉公人制度の色が濃い制度であり、外出の制限や休日、出世などのシステムはほとんど変わりません。仕着とは盆や正月に出す衣類や小遣い等の支給品のことであり(後に賞与へと変化しました)、別家とは奉公していた主の元から独立することを別家(分家ともいう。いわゆる「のれん分け」みたいなもの)と表現していました。
従来の奉公人制度からの変更点としては、暑中や帰国等の特別休暇を認める、結婚を早めにして通勤を許可する、独立した別家に同じ地域内での営業活動の禁止をする、あるいは別事業を任せてそのまま独立させるといった点でした。
独立の際の別家料は主が準備しますので相当の負担になりますが、これは主の裁量と判断によるものなので、評価によって厚い待遇を受ける人もいれば、そうでない人もいたようです。また、現在でいう退職金のように、別途積立てを行い、独立とともにそれを付与する場合もありました。
住み込み給料制とは、給料をもらいながら住み込みで勤務し、得た給料で衣服や身の回り品を購入し、他に教育費、治療費等を自らで賄うというものでした。
新しく入社した従業員に対しても給料を支払うので、企業側にとっては結構なコスト増となりました。企業によっては、在所登り制度といった仕組み(今のジョブ・ローテーションと似た仕組み)もあり、本店と支店とを5~7年ごとに行き来することで従業員の資質を判断し昇降格させる企業も出てきました。
やがて、企業規模が大きくなってくると新規採用人数も多くなり、住み込みで働くことは不可能となって、労働形態は通勤給料制へと変化していきます。
通勤給料制は、従業員に通勤させつつ給料を支払うという制度であり、現在の働き方に近いものです。この通勤給料制をいち早く取り入れたのは三井呉服店であるといわれ、明治の中頃から、最初から読み書き算盤やしつけがなった者を厳しい採用基準で選抜して採用していました(いわゆる新卒採用です)。これにより、優秀な人材を何年もかけて育成し選別していた従来の方法から数か月の試用期間で選別できるようになり、また毎年のように採用することができるようになりました。こうした通勤給料制を行なえるようになった背景としては、国が行う教育が体系化され、国民の多くが一定の学力を身につけるようになったことが大きいといえます。
また、折衷制といって、こうした通勤給料制と従来からの仕着別家制の両方のシステムを併存させていた企業もありましたが、丁稚上がりの従業員と大学卒業の従業員との間での対立が起こるなどして次第に会社員制の形へと落ち着いていきました(現代社会の高卒現場上がり組と大卒キャリア組の対立のようなものですね)。
会社員制へと移行した大きな理由としては、元々別家して独立するのが主だった商売が企業内で新規の支店出店、新事業の展開と同一企業内で活躍する場が多く提供されるようになったため、次第に会社員制が主流を占めることとなったのです。こうした動きは当初、中央で始まり次第に地方へと広がりを見せていきました。冷ややかな目で見ていた地方企業も、中央で成功していく企業を見て我先にと変革していったのです。
採用対象者も、従来は地元の縁故採用が主だったものが、学校卒業者が主となるようになり、人数もわずかだったものが、直営する支店等の拡大に伴って大規模で採用するようになりました。こうした事業規模の拡大に伴い、各地方に留まっていた商人は海外を含む各地域に拠点を置く企業へと変貌を遂げたのです。
会社員制を取る企業では、一定以上の学力を持つ従業員が勤務しますが、毎夜のように外部講師や年長者が講義を行い、商売に関する一般常識、数学、国語、英語、商品知識などを学ぶようにさせました。休日も月に1~2回程度であったことから、理論と実務とをみっちりと経験する場があったことが窺えます。
三菱では、明治の終わりごろから新規学卒者の定期採用を開始し、大正・昭和にかけて昇進昇格を重ねて定年退職に至るという終身雇用・年功序列の体系を作り上げていきました。このように、奉公人制度は徐々に崩れていき、会社員制度へと移行していったのです。
会社員制へと移行するなかで、より長期的に活躍してもらおうと勤続年数に応じて昇給する勤続給や年齢に応じた年齢給、賞与、通勤手当や住宅手当を含む各種手当も加わるようになり、今でいう年功序列や終身雇用の基盤ができてきました。
②内部請負職人の直接雇用化
江戸時代、職人は組合組織として「仲間」を持ち、その技術が拡散して希少性を失うことのないように一定の制限をかけていました。仲間になるには、まず職人の親方に弟子入りし、一定の修行期間を経て一人前の職人になる必要があったのです。一人前の職人になると、「鑑札」と呼ばれる札を所持し、さらに親方・棟梁になるには、仲間の「株」を持つ必要がありました。一職人が親方になるには、非常に長い年月と苦労が伴うものだったのです。今でも建設関係ではこれに近い習わしがありますよね。
こうした職人の独占的な分野も、明治時代以降徐々に企業の中に組み込まれていくことになります。電気・機械や重工業等で近代化が進み工場の稼働が始まると、個人の熟練度に頼っていたものづくりが均質で標準的なものづくりへと移り変わっていきます。
当初、工場は生産工程の一部を親方組織に業務委託し、親方が抱える弟子や再委託する職人で業務を遂行、納品することで、工賃を預かった親方がその弟子や職人に配分するという内部請負制を敷いていました。しかし、こうした内部請負制は製品の品質や納期にバラつきがあること、また新規技術の獲得に意欲的な親方とそうでない親方とに分かれてしまい、効率的なものづくりができないという問題点に直面しました。
そこで、企業は内部請負制から自社での直接雇用へと切り替えていき、親方組織ごと企業に組み込んだり、また職人を社員として雇い入れて指示命令系統を明確にすることで問題を解決していきました。働く側の職人も、生活のほぼ全てを握られていた親方に比べれば、企業の中で職人として安定的に勤務するほうが自由もあったわけです。こうして親方や組合組織は徐々に衰退していきました。
職人としての技術はやがて、明治時代に設立された官営工場等で活用されるようになっていきました。軍事工場や造船所などが次々と出来、鍛冶や鋳物の加工技術が必要とされたからです。このような職人は定雇職工として重宝され、かなりの厚遇であったようです。
たとえば、官営工場として創業した八幡製鉄所も、当初は内部請負制を敷いていましたが、明治33年には職工規則を規定。雇用対象年齢を満16~50歳以下とし、退職は満55歳とするなどして徐々に職工が増加し、定着率も高まるようになりました。こうして、独立稼業であった職人たちは、企業の事業活動の中に取り込まれていったのです。
③基幹社員と一般工員の格差
大正から昭和の初期にかけて、企業では等級制度が敷かれるようになり、基幹社員とその他の一般工員との格差も同時に広がっていきました。格差としては、労働時間、休日、給与、賞与、退職金等の全般で目を見張るほどの違いが出てくるようになりました。
基幹社員の役割は、今でいう取締役や部長などの経営管理職に該当し、一般工員の給与の20~50倍ほどの収入でした。基幹社員は、日給制か月給制が主であり、一般工員は日給制、時給制、出来高制、請負制と支給形態にも違いがあったのです。戦後、この格差が不当かつアンバランスであるとして、労働組合の運動が盛んになり徐々に解消されていくこととなります。こうした格差があったという事実については、戦前のほうが資本主義の色が非常に濃かったといえそうです。
④養成工制度による技術者の養成
江戸後期より昭和初期にかけて、工場制手工業が中心だったものから、作業が簡易化された軽工業や機械操作がメインとなる重工業へ、そしてオートメーション化が進んで大量生産が可能になりました。この標準化、自動化、工程化が進んだことで従業員に求められる資質や技術が大きく変化しました。
工場制手工業時代には製品を作るための熟練度が要求されていましたが、時代が進むと単純作業を効率よく行う力や新たな作業に適応する力が求められるようになり、工場で勤務する従業員も数多く必要とされました。
また、手作業だったものは機械操作に取って替わり、複雑化していく生産工程に対応するために、生産ラインの立ち上げから工程管理・品質管理、保全業務までに及ぶ、これまでとは別の知識や技能を求められるようになります。
そうした背景から、技術を持つ職人たちは自身の技能を高く買ってもらおうと転職を繰り返すようになり、企業も手を打つもののあまり成果が上がりませんでした。技術の積み上げが企業の資産になり競争力になるわけですが、それが流出するとなるとまた新たに育成していかなくてはなりません。
このように、求められる技術の高度化と定着率の悪化に対して根本から手を打つために、企業は「組織人としての教育」と「生産工程に求められる必要な技能教育」とを実施する企業内学校を作りました。これが養成工制度なのです。養成工制度として有名なのは、三菱長崎造船所に設立された三菱工業予備学校です。
養成工制度は、まず教育訓練として通常の作業時間内に教室内で座学を行い、OJTで体験を積み重ねて技能の習熟を図ります。一定の知識と技能を満たした職人は、部署に配属となり、作業を行うかたわら作業前・作業後の座学を学んでいくことで一人前の職人へと育つように体系化されました。教育期間は通常5年ほど設けられ、その後3~5年ほどは「退職できない期間」が設けられることとなりました。この仕組みにより、定着を図っていったのです。このほか、学年が上がるにつれて徐々に給与額が上がる企業や新規学卒者のみならず中途入社者に対しても教育訓練を施すといった企業もありました。
養成工制度は日本独特の雇用慣行であり、諸外国にはほぼ見られない制度です。養成工制度を採ることで、各企業は相当の負担を強いられましたが、定着率の向上が期待できるばかりでなく、自社の機密情報や独自技術を守り育て、長期にわたって忠誠を誓い貢献する企業人の育成に資することとなります。
明治時代の初期まで続いた商人の奉公人制度や職人の組合組織は、時代の流れに伴って形を変え、企業における養成工制度という形となっていきました。こうした日本人独特のDNAが戦後も生き続けることとなったことはいうまでもありません。現在も、日本の大手から中堅企業に至っては新卒採用が主流であり、企業が責任をもって新人を育成していくというスタイルは受け継がれているのです。
以上、明治時代から昭和初期にかけて急速に近代化が進んだのは、事業規模(組織化)が拡大し、技術革新(工程化・専門化)が起こったからに他なりません。しかし、その根底には以下の3つが複合的に絡み合ったことも、加速させた要因であると考えられます。
①基礎的な義務教育の浸透が即戦力化を促進した
江戸時代までは体系的ではなかった基礎的な義務教育が、明治時代に入ってから国民の多くに浸透していきました。知識偏重ではあったものの、それまで読み書き算盤は特定の人間にしかできなかったと考えると、全体が底上げされたことによって多くの能力が開花したことは言うまでもないでしょう。企業においては必要な義務教育を修了した者を採用できるということは、大幅な時間短縮=即戦力化につながったといえます。
②日本的道徳観や規律性の高さが組織化を促進した
日本人の高潔さや道徳観、規律性の高さは世界でも類を見ませんが、こうした日本人独特の感性が短期間での組織化を促したといえます。組織化によって指示命令系統が機能し、企業が自社独自の学校を組織し、上司や先輩が部下や後輩の面倒を見るという文化へとつながったことは企業内における人材の市場価値を急速に上げることに大きく貢献したと考えることができます。
③好奇心や勤勉さが事業の拡大を促進した
明治に入ってから全く異なる西欧文化が流入したことで、日本人の知的好奇心や勤勉さに火がつきました。新しいものを取り入れたい、豊かになりたい、という強い気持ちの表れが事業そのものの拡大に直結したといえます。特に、明治時代に大企業へと発展した多くの企業はいち早く海外へと拠点を構え、西欧と肩を並べて対等に商売していたのは驚きに値します。
これらのことは、明治時代だからというものではなく、現在でも全く同じことが当てはまると言えそうです。企業が強くなるには、一定以上の教育・しつけが必要であるということ、道徳観・規律性が重要になるということ、さらに好奇心や熱心さをもって事業を拡大していこうと動機づけていくことが求められるということです。
そして、日本は後進の先進国ながら西欧列強と肩を並べるほどの国力を増強し、やがて第二次世界大戦へと突入していきました。
2.戦後から現在に至るまで
「終身雇用」「年功序列」「企業別労働組合」という日本経済における三種の神器は、戦後に成立したという話があります。
実際、従業員の生活保障や立場の向上を求めた労働組合は、戦後になって活発になっていきましたが、もともとの年功序列の考え方は奉公人制度や職人の組合組織が主流だった江戸時代からありますし、終身雇用も明治時代後期から大手企業で技術の伝承や事業規模発展の観点から慣行的に行われていたといえます。
前述したように、明治時代から受け継がれた組織構築や人材育成の仕組みは戦後になって地方にまで浸透していき、日本経済の原動力となっていったわけです。
第二次世界大戦下では、昭和17(1942)年に施行された労務調整令等の各種法令と厳しい取り締まりから、転職や解雇が大きく制限を受けることとなりました。終身雇用は、大手企業においては既に慣行的に行われていましたが、法制化されたのは戦時下でした。こうした期間を経たことと三種の神器が日本の各企業で定着したことにより、諸外国と異なった「転職」「解雇」に対する否定的な価値観が醸成されていくこととなりました。(諸外国では逆に、転職や解雇(又は一時解雇)は否定も肯定もなくごく一般的なものであり、選択肢の一つでしかありません。)そして、戦後に焼け野原となった日本企業は再出発することとなります。
ここからは、戦後から現在に至るまでの人事実務(教育や人事制度)の変遷について、時代を追って見ていくことにします。
①戦後から1950年代半ばまで
戦後の日本は焼け野原となったために労働市場には人が仕事を求めて殺到し、賃金が下落、国民は日々の食べるものにも困るという厳しい状況に追い込まれていました。そのため、生活の安定と保障は、多くの人が望んだことでした。
そうしたなか、1946年に電力系組合である日本電気産業労働組合協議会が賃金制度として「電産型賃金体系」を提案しました。これは、後に日本における賃金体系の源流になっていきます。基本給の構成要素としては大きく「基本賃金」と「地域賃金」から成り、基本賃金は物価に連動した「生活保障給(本人給+家族給)」と、個人のスキルや能力、経験に紐づく「能力給」と、勤続年数に応じて昇給していく「勤続給」から構成されます。そのほか、特殊な勤務や僻地での業務については別途手当を支給するという制度となっています。当時としてはかなり合理的な賃金体系であったといえます。
全体の割合としては、生活保障給と勤続給が全体の7割程度を占めており、長く安定的に勤務すれば少しずつ昇給していくという年功序列要素の色濃いものでした。こうした賃金制度がスタンダードとなり、大手企業を中心に地方へと普及していくことになります。また、電産型賃金体系と共に、当時の労働省の指導により職階制度が導入されていきました。
1952年ころには企業経営が安定的になり始め、賃金水準もベースアップを行いながら回復していき、生活保障的色合いが強いながらも「学歴別賃金体系」が一般化していきました。その後から1955年にかけてデフレを経験した各企業は、賃金の一律ベースアップが企業経営を圧迫することに気づき、定期昇給を主とする制度へと転換していきます。学歴別の賃金体系と定期昇給の考え方が定着したのはこの頃といえそうです。こうして企業業績と労働力とのバランスを取りながら徐々に高度経済成長時代を迎えるようになります。
②1950年代半ばから1960年代半ばまで
高度経済成長を迎えると、労働力が不足して賃金が上がり、新卒採用時の年収も引き上がることによって賃金テーブルそのものの見直しが迫られるようになりました。
また、景気が全体に良くなったことで、従来の生活保障的な賃金制度ではやる気のある社員、成果を出す社員には報いることができず、従業員からの不満が続出することとなりました。そのような中、東京電力が、以前アメリカの労働諮問委員会から提案されていた職務等級制度と職務給制度を導入することとしました。
職務等級制度とは、各等級で担当する仕事の難易度や重要度、責任の大きさを決め、等級が上になればなるほど難易度や責任が伴う仕事を担当するようになる、というものです。仕事ごとに価値が決まるため、難易度や責任度合いが大きい仕事を担当する人ほど給与が高い、ということになります。職務等級制度・職務給制度では、勤続年数や学歴、家族構成は全く関係なく業務を遂行できるかどうかが重要であったため、電産型賃金体系とは相容れないものでした。
そのため、基本給を年功賃金と職務給とで構成する併存型としたり、職務給を主としながらも同一業務で昇給を認める混合型とするなどの工夫がなされました。しかし、結局のところ、この職務等級制度・職務給制度は時代や文化にマッチせず普及しませんでした。
その理由としては、以下のようなことが挙げられます。
・多くの企業は成長期にあり、事業拡大と共に業務の進め方も大きく変化する。制度導入時に一度、職務分析と評価を行なっても、その後の職務変化までを継続的に維持・管理するまで手が回らなかった。
・多くの企業では、社員がジョブ・ローテーションを経験しながら管理職のポストを目指す。職務で給与が異なる制度では、ジョブ・ローテーションの度に給与が変わるために生活が不安定になり、社員が配置転換を嫌がったり、会社側が給与を従前に据え置くなどして制度を維持できなかった。
・職務等級制度・職務給制度では、ジョブ・ディスクリプション(業務記述書)が必要となるが、日本の社会では業務範囲をあえて曖昧にし、本人の意欲や責任感でカバーする風土があるため、十分なジョブ・ディスクリプションが作成・維持されず、運用ができなかった。
こうして1960年の半ばには、企業は職務ごとに値段をつける職務給制度から、職務を遂行する能力(職能)に目をつけ始め、日本の文化にもマッチした職能資格制度が主流を占めるようになっていきます。
③1960年代半ばから1990年まで
社員をどのように評価し、昇給や賞与を以て意欲を駆り立てていくか、という試行錯誤を続ける大手企業は、職能等級制度・職能給制度へと辿りつきます。
職能等級制度・職能給制度とは、社員に求める「職務遂行能力(職能)」を等級で区分し、その等級ごとに給与を設定するというものです。その等級にいるということは、定義された能力を発揮できるはずだ、という想定のもとに格付けされます。職能が高まれば高まるほど企業に貢献しているということになり、その結果、等級が上がり給与が連動して上がる、という仕組みを取ります。
この制度は、同一企業内、又は同一業務を継続して経験していけば熟練度が上がり昇給していくという点で従業員側としては将来設計がしやすく、経営者側としても、年功制度や熟練度を要する業務にも対応でき、同一業務であっても評価によって昇給させたり等級を上げたりできるという点で、労使双方にとって大変使い勝手の良いものとなりました。そして、定期昇給の考え方もこの頃から、物価上昇に伴うベースアップと、年齢や勤続に伴う年功的な自動昇給と、評価による個人ごとの業績昇給の合計で行うという考え方に定着していきます。
また、賞与についてはこの頃にはすっかり給与の一部と化しており、従業員も年間で基本給3~5か月程度の賞与を当てにして住宅ローンを組み、大きな買い物をしていました。高度経済成長による豊かさを享受し、その豊かさがこれからも続いていくのだ、という前提に立ったものであったといえます。
やがて、1986年には、いわゆる男女雇用機会均等法が施行されることとなり、性別による取り扱いの格差を無くそうとする動きが進んでいきました。この流れを受け、企業では職群制度が導入されることとなります。職群制度とは、期待する役割や成果、業務内容により総合職と一般職とを区分し、給与や賞与、退職金などの待遇面に差をつけるというものでした。総合職と一般職とでは以下のような違いがあります。
・総合職:事業拡大のために、担当業務における問題発見や解決、新規事業の提案・遂行を主として行い、中核社員として成果を上げることが求められる職群。幹部候補として管理者を目指すコースであり、転勤にも応じることが一般的で、求められる成果や責任が一般職より大きいために待遇面も上となることが多いのが特徴。
・一般職:事業の安定的な運営のために、定型業務(ルーティンワーク)を主として行い、正確・迅速で効率が良い業務遂行を求められる職群。同一業務での末永い勤務が望まれ、転居を伴う異動はほとんどない。
今でも、新卒採用においては「総合職」と職種を銘打って行っていることが多いですが、この総合職という概念はこの頃に明確になったといえます。その後バブルが崩壊し、それまで高度経済成長を支えてきた日本的企業経営は大きく舵取りせざるを得なくなり、成果主義が台頭するようになります。
④1990年から2000年まで
高度経済成長による豊かさを享受した1980年代で職能等級制度・職能給は運用が甘くなり、制度疲労を起こすことになりました。当時、各企業は儲かっていたために総額人件費や個人ごとの評価を軽視し、勤続年数や年齢が上がれば「彼も生活があることだし、そろそろ上げようか」と半ば自動的に昇格や昇給を繰り返していく、という「単なる年功序列制度」となってしまっていたのです。
その結果、人件費が高止まりし、高止まりした割に成果が上がっていない、職能と給与にズレが生じる、という悪循環を生み、バブル崩壊による業績の縮小と共に人事制度の見直しが急務となりました。そのまま運用を続けると、企業経営そのものを更に圧迫してしまい株主から経営責任を問われるという非常事態だったといえます。
コストカットを目的とした人件費には、給与や賞与等の人件費の他に教育研修費や福利厚生費がありました。それまで行っていた階層別教育やテーマ別教育を最低限だけにする、退職金制度を変更する、社宅制度を取りやめる、運動会や社員旅行を中止する、といったものです。福利厚生については、これまでの手厚いものから気軽に利用できるカフェテリアプラン型のサービスを導入する企業が増加しました。
それまで良しとされてきた、日本的企業経営やビジネスモデルそのものが音を立てて崩れていくなかで、従業員を鼓舞し業績を回復させる仕組みとして「成果主義人事制度」が導入されることとなります。目標管理制度とセットにして導入されたこの成果主義は、「個人ごと」に「短期」の「成果」で測定され、成果に応じてインセンティブやボーナスが多く支払われたり、年俸が増減するという形態をとっていました。企業としては、成果が上がれば売上の中から一部を報酬として支払い、成果が上がらなければ支払わない、という明快なメッセージだったので、労使双方に納得感が得られやすい制度でした。企業内請負制のようなものと考えても良いと思います。
また、ライフサイクルが安定期にある企業においては、業務の進め方そのものが固定化しマニュアル化が進んでいきました。また、職能等級制度を現場で運用しきれないと判断し、職務等級制度や役割等級制度に切り替える企業が出てくるようになりました。
従来の日本型企業経営で特徴的な、業務全体の流れを理解させようと個人の守備範囲を曖昧にし、業務理解やスキルの熟練を5~10年単位で待つスタイルでは、自社の企業規模拡大にストップがかかってしまいます。これでは、現在のような変化の早い市場環境下では他社に競り負けてしまうことになりかねません。欧米のように、必要なマニュアルを整えつつ、各個人がどの役割・業務を担うのかが明確になっている職務等級制度のほうが変化に対応しやすいという判断から徐々に切り替わっているといえそうです。
⑤2000年から現在に至るまで
導入された成果主義は、実際に運用が始まってくるとその良さ以上に弊害が目立つようになりました。それは以下のようなものです。
・短期の目標達成を追求し過ぎて中長期の種まきをしなくなった
・責任者も部下と同様の目標を持ったため、目標達成しやすい大口顧客を責任者が持ち、そうでない顧客を部下が持つことで部下からの不満が出た
・経営者への見かけだけの派手なPRが増え、本質的で地道な目標達成が疎んじられた
・成果さえ出せば良いという発想から、プロセスがおろそかになった
・人材育成は評価対象外なので、上司や先輩が部下や後輩の面倒を見なくなった
・目標設定の際に簡単な目標を設定するようになった
・成果報酬がお金に偏り過ぎ、褒める、認めるという行為が減って職場がギスギスした
成果主義と目標管理は本来、相性は良いはずなのですが、この頃の日本企業は日本的経営が立ち行かなくなった時代でもあり、経営者だけでなく従業員も「何が正解かわからない」状態になってしまっていました。
目標管理は、目標(ゴール)が明確であり期限が決まっていて、プロセスも明確であるからこそ、定量的に測定することが可能となる仕組みです。にも関わらず、目標管理に対する理解が人事にも現場にも無いままに、一気に導入・運用されてしまったためにこうした弊害が出たといえるでしょう。
これらの弊害に対しては、チームで目標を追う、中長期の事業計画からブレイクダウンした目標を追う、業務プロセスを管理する、人材育成を評価に入れる、また職場内で認める、褒めるといった一体感を大切にする、といった対応を取り入れて軌道修正していくことが望ましいといえます。こうしたことに取り組んでいる企業もある一方、現場が多忙を極めるがゆえに上述の状況が続いている会社も多くあります。
また、この頃から、企業内における労使の一体感をいかに高めるかという視点でワークライフバランスや従業員満足(ES)の考え方が広まってきました。いわゆる育児介護休業法や労働契約法等の改正に伴う時代の流れに加え、成果主義に伴った金銭的報酬ばかりが働く目的ではない、との心理的な反発もあったと思われます。
組織の一体感を高めるために、各企業では独自の制度を設けるところも出てきました。フレックスタイム制の導入、長期休暇取得制度、海外留学制度、社内託児施設の設置、週休3日制、といったようなことです。職場でペットを飼う、職場近くに自宅を構える従業員に手当を出す、といった企業経営者が自由な発想で独自のルールを構築するようになってきたことは、狭い枠の中でしか発想してこなかった日本社会において、とても歓迎すべきことです。こうした制度そのものが企業のウリや独自性になり、人材がそこに集まり、その企業が成長し、その手法が広まって、やがてより良い働き方に繋がっていくと考えられるからです。
こうして、企業の在り方、働き方が各社で大きく異なるようになってきた、というのが現状です。
日頃から、人事コンサルタントとして外部から支援させていただいている側としては、本当に会社によって考え方や制度が異なることに驚きます。
それでも、そこで働いている従業員の皆さんにしてみればそれが当たり前であり、その中で自分らしく働く、自分らしい幸せを求めているといえます。そして、そこにどうしても自分らしさが見いだせなければ転職するか独立する、といった状況が今の日本社会です。
日本という島国で生き、働く中で、私たちは歴史や生まれ育った環境、世代性に囚われながら未来を創造しています。明治や戦後のように、次の時代を切り開いていったのは若手であり、彼らをバックアップしていた年輩がいました。今の時代も、若手が縛られたり閉塞感を味わうのではなく、次の時代を堂々と切り開けるよう支援し、環境を整備していくことが、私たちがすべきことではないかな、と考えます。
皆さんは、この組織と人事の歴史を知って、これからをどう創造していきますか?

ココロデザイン株式会社 代表取締役一本 亮
1978年生まれ。福岡県福岡市出身。東京海上日動火災保険株式会社等の勤務を経て、健康食品メーカーであるキューサイ、化粧品や医薬品を製造販売する新日本製薬の人事部門で組織編成を始め、採用・教育・人事制度・労務管理等の人事実務全般に従事し、制度設計と運用の両面で成果を残す。
2014年ココロデザイン株式会社を設立、ベンチャー企業~東証一部上場企業に至る人事戦略から実務に至るコンサルティングを手掛ける。2018年、人事経験をベースに人材定着・育成に有効なクラウド型定着検査サービス「ココトレ」をリリース。中小企業のみならず上場企業や大学等の教育機関も活用。